バイクの維持費はどれくらい?内訳や抑える方法を解説!
公開日:2024.03.31 / 最終更新日:2024.04.21

バイクを所有した場合に必ず発生するのが維持費(固定費)です。
毎年春の軽自動車税の支払い、強制保険とも呼ばれる自賠責保険への加入、排気量が250ccを超える場合の定期的な車検と重量税、これらが固定費となります。
さらには交通事故や各種トラブルに備えての任意保険と盗難保険、月々の駐車場代や車両のローン代、ガソリン代、点検・メンテナンス代といったものが変動費です。
「バイクはそんなに金がかかるのか!?」と思われそうですが、月々の支払いを少なくする方法や考え方についても説明します。
バイクの維持費(固定費)
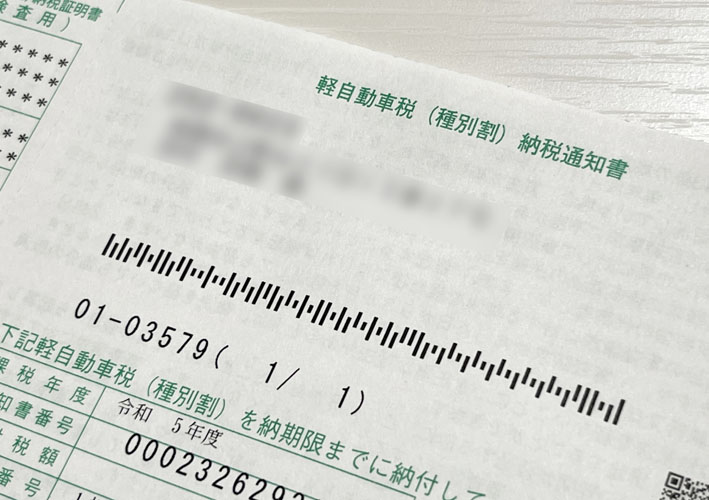
税金や保険など、バイクを所有する上で必ず発生する費用(固定費)について説明します。
軽自動車税
毎年4月1日時点で所有している原動機付自転車、二輪車などにかかる地方税(市町村税)です。5月上旬くらいに納税通知書が届き、5月末が納期限となります。排気量別に税額が異なっており、一度に1年分の税金を納める仕組みです。
軽自動車税の区分・排気量と税額
| 区分 | 排気量 | 税額 |
| 原付一種 | ~50cc | 2,000円 |
| 原付二種 | 51~90cc | 2,000円 |
| 91~125cc | 2,400円 | |
| 軽二輪車 | 126~250cc | 3,600円 |
| 小型二輪車 | 251cc~ | 6,000円 |
乗っていないバイクなら廃車する手も
廃車手続きをしない限り乗っていないバイクでも所有しているだけで毎年かかる税金です。4月1日より前に廃車手続きを済ませてしまえばその年の軽自動車税はかかりません。
自賠責保険
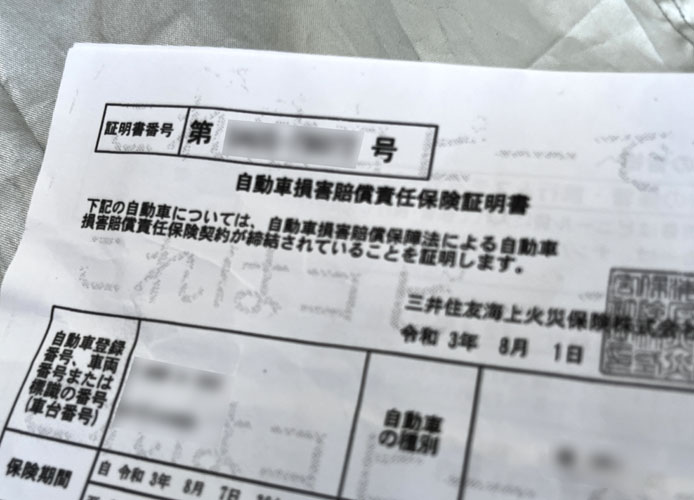
正しくは自動車損害賠償責任保険と言い、強制保険とも呼ばれ、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられています。
公道を走る場合は加入する必要があり、加入しないで運転した場合は50万円以下の罰金または1年以下の懲役、違反点数は6点となり一発免停(免許停止処分)となってしまいます。
自賠責保険の金額は一定ではありません。交通事故数が減少し保険会社からの支払金が減った場合などは値下がりすることもあります。
公共性の高い保険なので利益も損失も出さないように調整・算出され、本土と離島など地域によっても金額が異なります。
2023年4月からは2年ぶりに値下げ(平均11.4%の引き下げ)となり話題となりました。
自賠責保険は保険期間を長く設定するほど1年あたりの保険料が安くなります。少しでも節約したい場合は長期で加入することをお勧めします。
仮に途中でバイクを売却・廃車するなどした場合でも自賠責事務センターに解約書類を送れば解約返戻金を受け取ることができます。
自賠責保険の金額
| 排気量 | 加入期間 | 金額 |
| ~125cc | 12か月 | 6,910円 |
| 24か月 | 8,560円 | |
| 36か月 | 10,170円 | |
| 48か月 | 11,760円 | |
| 60か月 | 13,310円 | |
| 126~250cc | 12か月 | 7,100円 |
| 24か月 | 8,920円 | |
| 36か月 | 10,710円 | |
| 48か月 | 12,470円 | |
| 60か月 | 14,200円 | |
| 251cc~ | 24か月 | 8,760円 |
| 25か月 | 8,910円 | |
| 36か月 | 10,490円 | |
| 37か月 | 10,630円 |
※沖縄県・離島などの一部地域は額面が異なります
どこの保険会社でも保険料は同じ
自賠責保険は政令で定められているため、地域が同じならばどこの保険会社で加入しても保険料は同じです。
250cc以下ならコンビニでも加入できる
代理店(バイク販売店等)や保険会社でなくても250cc以下のバイク(車検の必要ないバイク)ならインターネットやコンビニエンスストアのマルチメディア端末、郵便局等でも加入・更新ができます。
車台番号とナンバープレートの番号が必要になるので控えておきましょう。
車検費用

250cc超のバイクで公道を走るためには車検を通す必要があります。車検の間隔は新車購入後の初回のみ3年間、それ以降は2年ごとです。
車検は、ユーザー個人が検査場(各地にある陸運局の運輸支局または検査登録事務所)に車両を持ち込んで検査を受けるユーザー車検か、バイク販売店・用品店・代行業者などに依頼して行うことが一般的です。
お店に依頼する場合、数日間は車両を預けることが多いので代車を借りれる場合もあります。

検査場はいつも混んでいますが、中でも販売店の決算や新生活キャンペーンなどが集中する3月が最も込み合います。
自分で通すにしろお店に依頼するにしろ、この時期はなるべく早めに検査を済ませると良いでしょう。
車検は車検証に書かれている検査満了日の1か月前から受けることができます。逆に閑散期は4~10月とされています。
なお、運輸局指定工場(民間車検場)を完備したお店に依頼すれば、検査場まで車両を持ち込まなくてもお店の設備で検査ができるので、その日のうちに素早く車検を通すこともできます。
お店に依頼するなら5万円~が目安
車両の状態によって一概には言えませんが、車検をお店に依頼する場合は必要な点検・整備を含めて、安くても5万円以上はかかるケースが多いです。
ユーザー車検で自ら検査場に持ち込む場合は消耗品の交換や大がかりな調整・修正がなければ2万円以内で済むこともあります。
重量税
重量税はすべてのバイクに毎年発生するわけではありません。原付一種・二種には発生せず、軽二輪は新車購入時のみ発生します。
また、車検のあるバイク(小型二輪)の場合は車検を通すときに初年度登録年数に応じて次の車検までの2年分を前払いする形になります。
重量税の区分・排気量と税額
| 区分 | 排気量 | 税額(年間) |
| 原付一種 | ~50cc | 課税なし |
| 原付二種 | 51~90cc | |
| 91~125cc | ||
| 軽二輪車 | 126~250cc | 4,900円(新車登録時のみ) |
| 小型二輪車 | 251cc~ | 1,900円(登録後12年目まで) |
| 2,300円(登録後13~17年) | ||
| 2,500円(登録後18年以上) |
バイクの維持費(変動費)
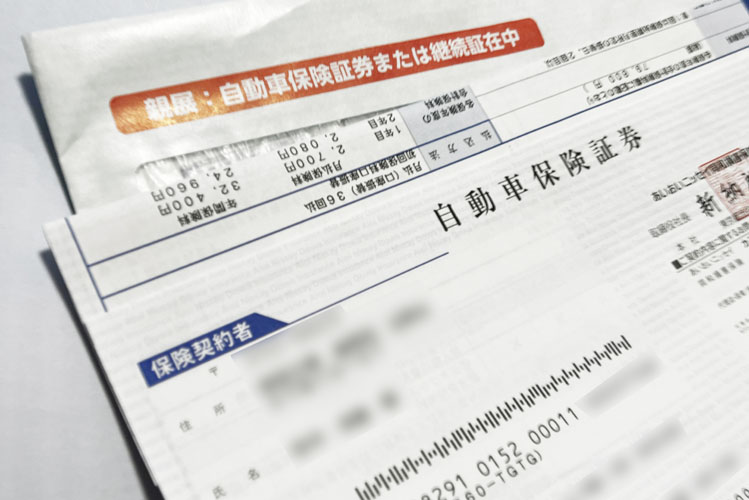
バイクを所有していても必ず発生するわけではありませんが、よく必要とされる変動費について説明します。
任意保険
主な加入の目的は交通事故への備えです。
交通事故では対人・対物などで高額な保証金額となることも珍しくなく、人身事故の対人損害賠償に限られている自賠責保険(最高120万円しか補償されない)ではまかないきれないことも多いため加入しておくことを強くお勧めします。
自賠責保険と同じく任意保険も車両に対して掛けるものです。
複数台のバイクを所有している場合、すべてのバイクに掛けようと思うと高額になってしまいますが、自分のバイクやケガの補償も受けられるので公道を走るのであれば可能な限り掛けておくことをお勧めします。
保険金額はバイクの排気量や補償内容、年齢や等級、年間予定走行距離、免許証の色などによって変わってきます。基本的に事故のリスクが高いとされている10~20代のほうが高い金額に設定されています。
事故対応だけでない任意保険の魅力
現在は「バイク保険」という名目で、損害賠償などの事故対応だけでなく、トラブル時のレッカー搬送といったロードサービス、帰りの足代やホテル代まで出してくれる付帯サービスを持つ保険も多く、任意保険への加入=事故に備えるというだけでなく、バイクに関わるトラブルや困りごとを広くサポートしてくれる保険として認知されています。
駐車場代

バイクを所有するにあたり自宅に駐車スペースがない場合は近隣の駐車場を借りることになります。
月極駐車場の場合は毎月賃料を支払いますが、初期費用が掛かる場合もあります。
賃料は地域や地価、駅からの距離、駐車場設備などによってまちまちです。青空駐車場(砂利か舗装か)、屋内駐車場(自転車置き場かバイク置き場か)、コンテナスペース(ガレージスペースがあるかないか)などで賃料は大きく変わります。
防犯カメラや通報設備、防災設備などが整っている駐車場が理想ですが、すべてを備えた駐車場は多くありません。
ローン代
バイクをローン(分割)で購入した場合は月々の支払いが発生します。
利息の高い消費者金融や信販会社から銀行など金利の低いところに借り換えるなどして月々の返済負担を軽くすることもできます。
ガソリン代

バイクに乗れば乗るほど、走れば走るほどガソリン代がかかります。近年は原油価格の高止まりによりガソリン代が高騰しています。
ガソリンスタンドで発行している会員カードや会員アプリへの加入・使用、提携ポイントカードの利用などにより、リッターあたり数円お得に給油できる場合もあります。
メンテナンス費用
バイクは走行距離が延びるほど、消耗品や油脂類の交換といったメンテナンスが必要になります。
走行距離や期間を目途とした点検内容とその頻度は、バイクの取扱説明書に書かれています。
工具やケミカル類を購入して基本的なメンテナンスを自分で行えば費用を抑えることもできます。
バイクごとにメーカーから発行されているサービスマニュアルやパーツリストを購入すれば、さらに踏み込んだメンテナンスを行うこともできます。
点検費用
日々のメンテナンス(日常点検)に加えて、定期点検(法令では1年ごと)を受ける場合は費用が発生します。
バイク販売店から1年点検(12か月点検)の案内が届くこともあります。
車検のない250cc以下のバイクにとっては特に重要な点検となります。
点検費用はお店によって多少異なりますが、部品交換が必要な場合は部品代と工賃が加算されます。
定期点検を自分で行えば費用を浮かすこともできますが、道路運送車両法により点検整備記録簿の作成・管理などが必要になります。
また点検と整備は別物ですので、必要とあらば記録簿を持ってお店に整備を依頼しましょう。
点検整備記録簿はバイクの取扱説明書やメンテナンスノートに付属しています。インターネットからダウンロードもできます。
バイクの年間維持費の例

バイクの維持費について筆者の例を紹介します。車体の状態により車検はユーザー車検で通すこともあるので、あくまでも参考程度と考えてください。
筆者(50代・神奈川県在住)の維持費例
メーカー:Honda
車種名:CBR1100XX Super Blackbird(1997年式EU仕様)
排気量:1137cc
使用用途・頻度:仕事の移動とツーリング・週に2回以上は高速道路を利用
年間走行距離:約8,000km
| 軽自動車税 | 6,000円(1年分) |
| 自賠責保険 | 8,910円(25か月分) |
| 車検費用 | 約6万円(2年ごと・販売店依頼時) |
| 任意保険 | 24,210円(1年分) |
| 盗難保険 | 16,500円(1年分) |
| 駐車場代 | 20,000円(1か月分・車1台分を月極契約しバイク2~4台置き) |
| ローン代 | 15,000円(1か月分) |
| ガソリン代 | 約80,000円(平均燃費はリッター15km) |
| メンテナンス費用 | 17,100円(オイル、ブレーキパッド、ステップラバーなど消耗品の部品代・工賃)
※カスタム費用は除く |
| 点検費用 | 17,500円(12か月点検・販売店依頼時) |
| 1年あたりの費用 | 494,874円
※駐車場は常時2台置きなので10,000円/月で計算 |
ローン代は支払いが終わればゼロになるとしても駐車場代は高額に感じてしまいますね。
駐車場代を理由に引っ越しをする人の気持ちがわかります。
バイクの維持費を抑える方法

ここからはバイクの維持費を少しでも抑えるための様々な方法を紹介します。
自賠責保険の長期加入
自賠責保険の項目で前述しましたが、長期間で契約してしまうほうが1年あたりの保険金は安くなります。
任意保険を見直す
任意保険は保険会社や契約プラン、付帯サービスの内容などによって金額がかなり変わってきます。いま加入しているプランが最適かどうか、他の保険会社で同じような補償内容で安いプランはないかなど見直してみるのも手です。
燃費を意識した走りをする

急のつく動作をしないなど日ごろから燃費を意識した走り方を心がけて少しでもガソリン代を節約します。高速道路ではなるべく上のギヤを使うなどして回転数を落として走るのも有効です。
点検・メンテナンスをしっかり行う
洗車をまめに行う、燃費や安全に直結するタイヤの空気圧をしっかり管理するなど日々の点検をしっかり行うことで異変や異常に早く気づけます。大きな出費となる前にメンテナンスしましょう。
消耗品のグレードを見直す

エンジンオイルなどは銘柄やグレードによって価格が大きく変わります。
サーキット走行などエンジン性能をフルに使うような走りをしないのであれば、ベーシックグレードのものを早めのサイクルで交換していったほうが劣化や性能低下を防ぎ、結果的に安くつくこともあります。
バイクの維持費の考え方、特に20代のライダーへ

今回、筆者自身の大型バイクの維持費を算出してみましたが、意外に大きな金額で驚きました。
バイクを買おうと思い立ったとき、その後の維持費まで考える人がどれだけいるでしょうか? おそらく少ないと思います。
2023年は全国的にバイク事故死者数が増加しましたが、そのうち特に多かったのが20代と60代です。
独身であれば20代でバイクを買うこと、維持することはそれほど難しいことではないかもしれません。
しかし事故の多い世代ということで任意保険はかなり高額で、保険会社やプランによってはひと月で14,000円ほど、年間で17~20万円くらいの場合も珍しくありません。
この金額を維持費にしっかり組み込んで上でバイクに乗り出してほしいと筆者は考えます。
交通事故を起こしてしまったとき、自分が250ccバイク、事故の相手が高級外国車だったとすると過失割合でこちらが有利だったとしても相手車両への支払いは自賠責保険(対人・被害者のみ)は使えません。
こうした事故時の想定をもとに、任意保険への加入やドライブレコーダーの装着にもお金を使うことをバイク購入時にしっかり考えるようにしてください。
安全第一があってのバイクライフ、バイクの維持費なのですから。












